
バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックは、化石資源由来のプラスチックに代わる環境にやさしい素材として、世界中の企業、消費者から注目されています。
環境負荷が低い素材である点は共通ですが、バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックには、原料や機能に大きな違いがあります。
今回は、バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの違いをご紹介しながら、それぞれの代表的な種類、求められる用途などについて解説します。
目次
バイオプラスチックの中のバイオマスプラスチックと生分解性プラスチック

植物などの再生可能な有機資源を原料としたバイオマスプラスチック(非生分解性)と、微生物などによりプラスチックをH2O(水)とCO2(二酸化炭素)に分解する生分解性プラスチック(化石資源由来)の総称がバイオプラスチックとされています。
ここから、バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックのそれぞれの原料や特性をご紹介しながら違いを明確にし、使用シーンや解決すべき環境問題について考えていきます。
バイオマスプラスチックとは
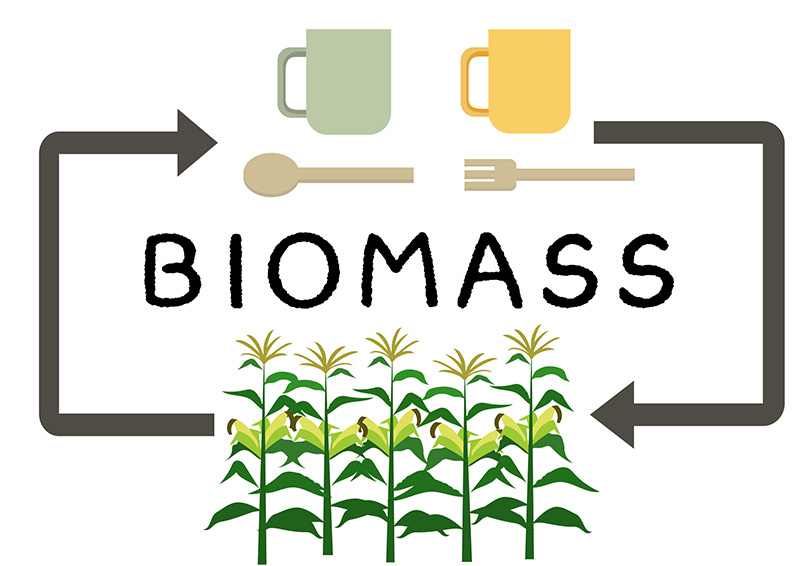
バイオマスプラスチックとは、再生可能なバイオマス資源を原料として、化学的または生物学的に合成することにより得られるプラスチックと定義されています。
一般的にバイオマスプラスチックの原料には、1〜10年間の比較的短いサイクルで再生産することができるトウモロコシやサトウキビなどの有機資源が利用されています。
この原料のバイオマスは、成長過程で光合成を行い、大気中のCO2(二酸化炭素)を吸収してO2(酸素)を生成します。
しかし、バイオマスプラスチックの廃棄時には、一般的なプラスチックを焼却した時に生成する熱エネルギーは排出しませんが、CO2は発生します。
つまり、バイオマスプラスチックは、生成から廃棄されるまで、CO2は排出された分、吸収もされているとし、トータルCO2排出量が±0であるいう考え(カーボンニュートラル)のもと、地球温暖化防止に有効な素材として使用されています。
日本国内では複数のバイオマスプラスチックに関連する協会が、バイオマスプラスチックを細かく定義していますが、バイオ由来の炭素と石油由来の炭素が混ざっているプラスチックもバイオマスプラスチックに含んだものとして分類しています。
ここでは、100%バイオマス由来のプラスチックで、非分解性のもの(自然界に分解しないもの)の具体例を紹介します。
バイオPE(ポリエチレン)
バイオPE(ポリエチレン)とは、主にサトウキビを原料としてつくられたプラスチックを指します。
身の回りの具体例としては、コンビニやスーパーで使用されるレジ袋が挙げられます。バイオプラスチックの中で、最も日常的に使用されており、知名度が高いバイオマスプラスチックと言えます。
バイオPP
バイオPP(ポリプロピレン)とは、バイオPEと同様にバイオマス資源を原料とするポリプロピレンを指します。農作物や食品廃棄物、食用残渣油などを原料としており、自動車部品や食品容器など様々な分野で私たちの暮らしに欠かせない素材として使用されています。
バイオPPはバイオPEに次ぎ、日本で生産されるプラスチックの2割程度を占める主要な素材です。
生分解性プラスチックとは

生分解性プラスチックとは、自然界に存在する微生物などの働きにより、プラスチックをH2O(水)とCO2(二酸化炭素)に分解するプラスチック素材の総称を指します。
しかし、生分解性プラスチックは、堆肥環境や土壌環境、海洋環境などの分解条件の違いによりさまざまな種類に分けられるほか、原料もバイオ由来のものや石油由来のものもあり、多様な種類が存在します。
以下に、原料別に代表的な種類をご紹介します。
バイオ由来
バイオ由来の生分解性プラスチックの具体例として、PLA(ポリ乳酸)やPHA (ポリヒドロキシアルカン酸)が挙げられます。
PLAは、微生物発酵による乳酸(トウモロコシやイモ類など)を原料とした重合体で、硬質プラスチックとして使用されています。
PHAは、ヒドロキシブタン酸の重合体で、脂肪酸や糖を微生物発酵させて生成されるポリエステルです。さまざまな生物有機資源から合成でき、土壌や海洋、河川など多様な場所にPHAを分解する微生物が分布することも特徴です。
バイオ由来+化石由来
バイオ由来と化石由来のハイブリッドの生分解性プラスチックの具体例として、バイオPBSやPBATが挙げられます。
バイオPBS(ポリブチレンサクシネート)は、自然界の土壌の微生物によりH2O(水)とCO2(二酸化炭素)に自然分解される生分解性プラスチックです。高耐熱性で繊維などと融解しやすいため、工業製品(3Dプリンターのフィラメントなど)に採用されています。
また、PBAT(ポリブチレンアジペートテレフタレート)は、1,4-ブタンジオール、アジピン酸、テレフタル酸の共重合によって合成される樹脂です。身の回りでは、ラップやフィルム、コーティングなどに採用されています。
バイオPBSもPBATも廃棄時の環境負荷が小さいことが特徴であり、近年注目を集めている生分解性プラスチックの一つです。
化石由来
化石由来の生分解性プラスチックの具体例として、PVAやPGAが挙げられます。
PVA(ポリビニルアルコール)は、ビニルアルコールの重合体で、高い親水性が特徴のプラスチックです。現在では、農業用被覆資材などに利用されています。
そしてPGA(ポリグリコール酸)は、石油を原料として合成される脂肪族ポリエステルです。炭酸ガスや酸素ガスを透過させにくい性質があり、炭酸系の飲料水や液体調味料などのプラスチック容器に利用されています。
バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの違い
バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの違いは、原料と機能性にあります。
原料を比較するとバイオマスプラスチックの原料は生物由来(植物や廃棄物など)を基準としますが、生分解性プラスチックの原料は石油由来(非生物由来)のものも含んでおり、原料に着目すると、バイオマスプラスチックの方がCO2吸収と排出を考慮した素材であると言えます。
一方で、生分解性プラスチックは、廃棄された場合、自然界に存在する微生物によりH2OとCO2に分解され有害な物質は発生させないことから、生分解性という機能がある点では環境負荷の低い素材と言えるでしょう。
原料か機能性に着目するかの違いはありますが、バイオマスプラスチックも生分解性プラスチックも、化石資源由来のプラスチックに代わる素材として、存在意義が高まり世界中での普及が始まっています。
バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックが求められる用途

バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの原料や機能の違いはこれまでにご紹介しましたが、身の回りにある商品を例に挙げて用途を具体的に説明します。
バイオマスプラスチック
バイオマスプラスチックの用途は、食品などの容器・梱包資材、衣料(繊維)、電気機器部品、自動車内装部品、オフィス機器などであり、耐用期間が短いものから長いものまで多種多様に存在します。
地球温暖化問題に対し、SDGsへの具体的な取り組み・CSR活動の一環として、前記の商品や商品の一部にバイオマスプラスチックを採用する企業やメーカーが増えてきています。
生分解性プラスチック
生分解性プラスチックの主な用途は、土木資材・農業資材、ごみ袋、食品容器・梱包材などであり、比較的、短期間で使用され廃棄されることが多いものに使用されます。
そのため、長期的に雨や風、熱などの環境負荷を受け、早期に分解されると品質が落ちてしまうような、屋外や高温多湿の環境で使用されるマットなどの商品には不向きと言えます。
マルヰ産業は生分解性プラスチックを用いた製品開発も進行中

バイオマスプラスチックや生分解性プラスチックの研究・開発は、プラスチック開発・製造に携わる企業はもちろん、さまざまな分野で注目されています。
マルヰ産業でも、生分解性プラスチックは環境負荷低減効果の価値が高い素材として捉え、従来使用しているPET繊維などと近いことから、PLA繊維を用いた商品開発に取り組んでいます。
マルヰ産業は、自動車部品から建設業界に至るまで、日本のものづくりを影で支える「不織布」専門の製造・加工メーカーです。
普及には多くの課題がある生分解性プラスチックですが、弊社の製品に新素材として取り入れることで、生産活動を環境に配慮したものにできればと考えます。
マルヰ産業では、日用雑貨や土木資材用のフェルトも、ご希望に合わせてお作りしています。
「不織布やフェルトについてくわしく知りたい」など、疑問点やお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。
